第42回(2025年度) 受賞作品
|
|
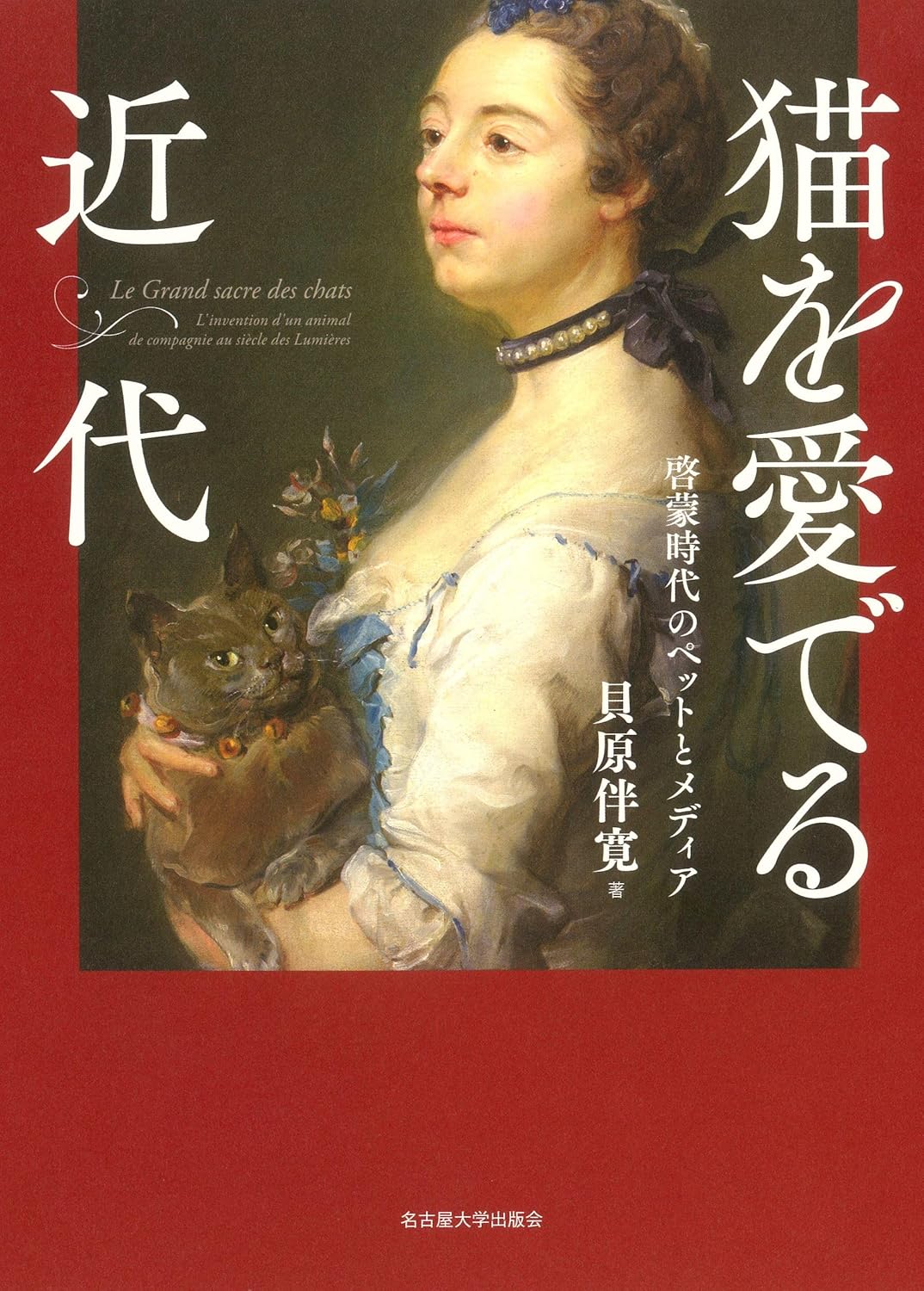 |
貝原伴寛 猫を愛でる近代——啓蒙時代のペットとメディア 名古屋大学出版会、2024 |
|
|
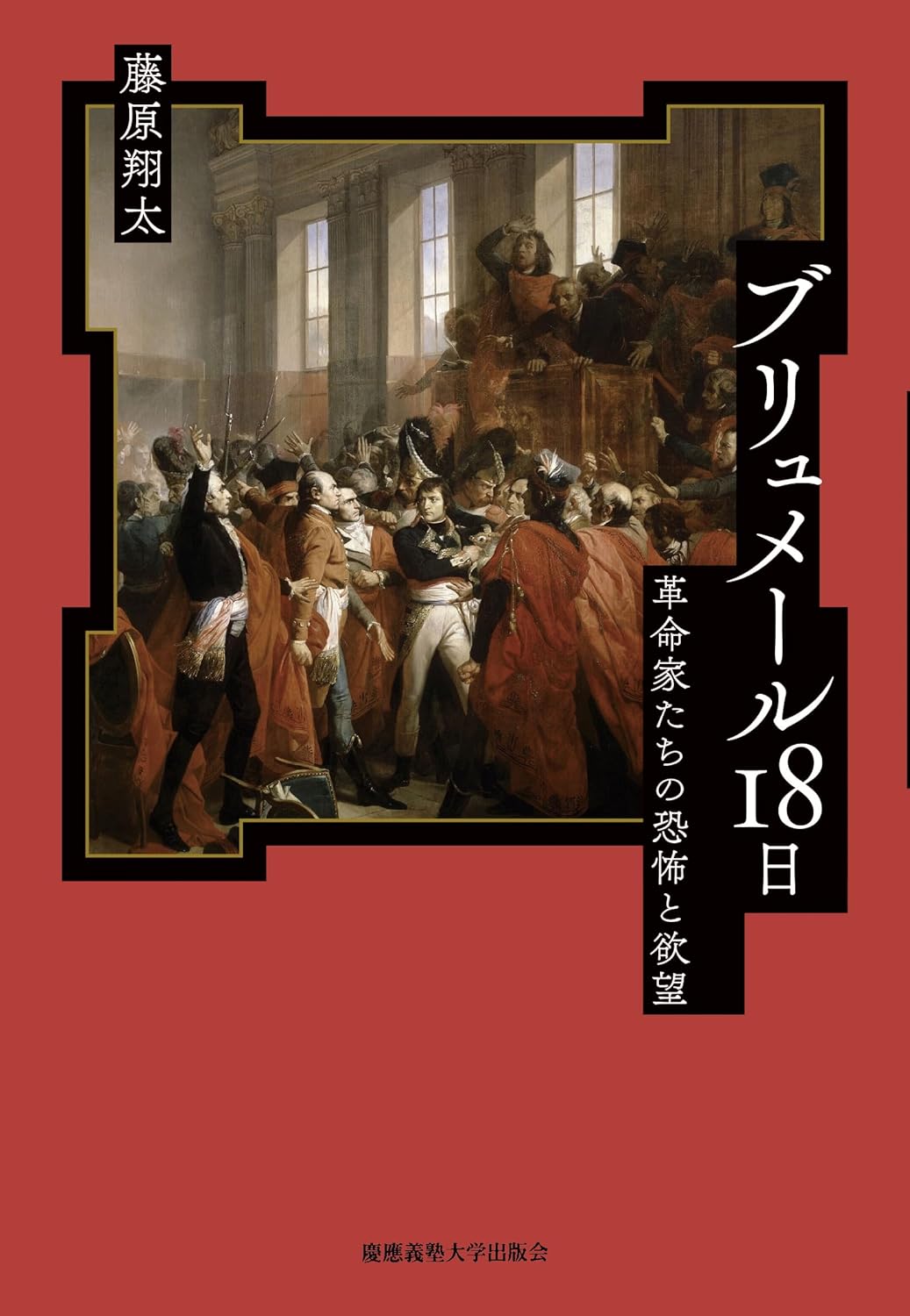 |
藤原翔太 ブリュメール18日——革命家たちの恐怖と欲望 慶應義塾大学出版会、2024 |
審査報告
公益財団法人日仏会館
渋沢・クローデル賞委員会委員長
中地 義和
今回の二つの受賞作はともに歴史研究です。時代的にも、近世から近代の黎明期を扱う点で近似性があります。ただし、テーマもアプローチも大きく異なります。
本賞を受賞した貝原伴寛さんの著書『猫を愛でる近代——啓蒙時代のペットとメディア』は、2023年3月に留学先の社会科学高等研究院で審査を受けた博士論文 « Le grand sacre des chats. L’invention d’un animal de compagnie en France (1670-1830) » をベースとする大著です。
猫は、今でこそ世界中で犬と並ぶ最もポピュラーなペットですが、元来、利己的で手なずけがたく、忠義を知らない動物という通念がありました。ねずみ駆除の効用に加えて、防寒具や民間薬の材料にもなりました。パリやメッスでは、キリスト教の祝祭で厄除けの火のなかに生きた猫が投げ込まれ、その阿鼻叫喚を人々が聴いて楽しむ、市当局公認の行事があったそうです。しかし18世紀になると、知識人は猫を殺す文化から距離をとり始めます。猫の焼き殺しは「残酷な迷信」として断罪され、猫薬も大革命以後の近代医学・薬学の教育機関では放棄されます。猫が反抗的なのは人間が野蛮に接してきたからではないか、という反省が生まれます。猫は有用性から切り離され、その存在自体によって飼い主の寵愛を受けるペットや伴侶として存在しはじめます。本書は、こうした変化がどのような条件のもとで一般化したのかを、言語や絵画の表象に着目して探ります。
猫の境遇が変化したのは啓蒙思想が因習を批判したからだ、とする観念的通説の限界を見抜く著者は、むしろ、猫殺しを残酷と感じ、有用性とは無関係に猫を愛でる感受性が、社会のエリート層の間で醸成されたからだと考えます。そのプロセスを解明すべく、一方では、猫が「社会的表象において馴致されていく」過程を映し出す実例を、科学思想、文学作品、ロココ絵画やサロン文化のなかに探ります。当時流通量が急増した書籍や版画から、私的書簡や未刊行の裁判資料に至るまで、幅広い素材が扱われます。同時に、猫を愛でる人々の表象が、それを観る(読む)公衆に及ぼした影響が考量されます。人と猫の現実的関係が種々の表象に反映し、また表象が現実的関係を変容させるという、18世紀の「メディア革命」が可能にした相互作用を、本書は鮮やかに炙り出しています。
こうして、猫を愛でることは奇異ではなく、それを表明することが社会的に許容されるという認識が優勢になり、「愛猫共同体」が形成されます。ただし、猫を主題とする史上初の書物とされるモンクリフ『猫』が例証するように、女性のために猫を賛美する著作に男性の領分とされる「学識」や「歴史」がもち込まれ、共通の古典的教養を有する男性読者が想定されていた、という隠蔽や捻じれを著者は喚起します。時代の多元的規制を浮き彫りにする興味深い指摘です。
愛猫という卑近な視点から啓蒙の時代を照らし出す本書は、「感情史」という新しい分野での瞠目すべき成果です。著者はまた、猫を完全に馴致することは、他民族に先駆けて「文明」状態に達したと自負するヨーロッパ人が、続く19世紀に「文明化の使命」を口実に行なう植民地侵略の予兆的エンブレムでもあることを、さりげなく暗示しています。明快で軽快な文体のなかにちりばめられた屈折や含みもまた、本書の魅力として高く評価できます。〈高度な学問的達成〉と〈読書の愉悦〉という渋沢・クローデル賞の二条件を満たす充実した著作です。
奨励賞を受賞したのは、藤原翔太さんの著書『ブリュメール18日——革命たちの恐怖と欲望』です。このクーデタ(1799年11月9日)は、従来、フランス革命末期に登場して、その華々しい軍功により一躍脚光を浴びるにいたった若き軍人ナポレオン・ボナパルトの権力欲が生み出した事件と解釈されてきました。著者はむしろ、諸々の矛盾を内包して弱体化した総裁政府(1795-99)の限界を見すえ、その原因である1795年憲法に代わる新憲法の制定を企てるシィエスら穏健共和派を中心とする「ブリュメール派」の政治家たちが、国民の間で絶大な人気を誇るナポレオンを担ぎ上げたクーデタと見ます。本書はフランス革命の帰着点であるこのできごとの理解に根本的修正をもたらす野心作です。
全体で二百頁ほどの小ぶりの著書ですが、時代の動き、政治家たちの思惑、さまざまなレベルの統制システムが、過不足のない明快な文体で記述されており、固有名詞の氾濫はともかくとして、一般読者にも十分楽しめる啓発的な読み物になっています。
ロベスピエールの恐怖政治が「テルミドール9日(1794年7月27日)のクーデタ」によって終焉を迎えたあと、革命政治家たちは、国内では革命独裁(ネオ・ジャコバン)と反革命勢力(王党派)との双方を抑え、対外的には第二次対仏同盟の圧力に対峙しながら、革命の成果たる共和政の完成を図ります。しかし1795年憲法に拠る総裁政府は、独裁を回避すべく五人の総裁の集団指導体制をとり、毎年一人ずつ改選されるうえに、法案提出権も議会解散権も有しませんでした。議会も、独裁を避けながら継続性を担保するするために毎年三分の一が改選され、総裁罷免権を有しませんでした。政府と議会が正面から対立した場合、機能停止となる危険がありました。
毎年の改選では、ときに王党派が多数を占め、ときにネオ・ジャコバンが優位に立ち、穏健共和派が主流をなす政府はそのつどクーデタに訴えて状況を覆す憲法違反を犯しました。不安定な政権運営は民心の離反を生み、国外の敵対勢力に付け込まれる隙をはらんでいました。シィエスと彼の同志たちは、絶対王政とも革命独裁とも無関係に強い執行権を有し、国民世論の信用を勝ち取り、国内外の危機を越えて国民の生命と財産を守れるような政府を作るべく新憲法の制定を企てます。そこで彼らが利用しようとしたのが、国民の英雄として人気を博すナポレオンでした。ナポレオンは、シィエスが彼に付与しようとした形だけの最高ポスト「大選任者」を拒否し、自ら「第一統領」に就きます。土壇場でブリュメール派の思惑を凌駕したナポレオンの野心はたしかに無視できませんが、本書は革命史の文脈のなかに彼の重みを相対化しています。
著者は、統領政府の中央集権体制強化策として、名士リスト制度に基づく選挙制度や任命制に基づく地方行政システム、「安全保障国家」たるに必要な「憲兵隊」改革や裁判官の任命制を軸とする司法改革について、新発見を交えて精緻に解説しています。審査会では、制度やシステムの解説は精確かつ簡潔で申し分ないが、政治家の人間像や思惑の叙述は淡白すぎないか、という留保が表明されました。本書の全体的構想、記述のエコノミーに照らせば、それは無いものねだりかもしれません。ともあれ、高度な学術的成果を平易な言葉で、という渋沢・クローデル賞の要請に、本書は見事に応えています。
貝原さんと藤原さんに心よりお祝いを申し上げ、今後のさらなる発展、新たな展開を期待します。


